
須曽蝦夷穴古墳
石川県も遺跡の多い土地ですが、その中でも須曽蝦夷穴古墳は一風変わった古墳です。
この古墳は海の見渡せる場所にポツンと作られています。
大きな特徴は、1つの墳丘に2つの埋葬室が作られているのです。
「雄穴」と「雌穴」と呼ばれています。
高句麗の古墳との関連性が指摘されているそうです。
ここではバスの運転手さんから橋が出来る前の様子を聞いたり、須曽バス停では地元のおばあさんに色んな話を聞きました。
遺跡も良かったですが、人とのふれあいも楽しかったです。
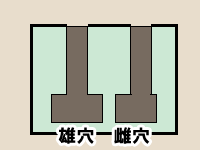
イザ!須曽蝦夷穴古墳へ!
 |
 |
 |
| つじ薬局前のバス停から出発します。 バスは能登島交通を使います。 早朝のバスを選んだので誰もいません。 |
バス停「須曽」に到着。 ここから少し歩いて古墳へと続く横道へ向かいます。 |
この看板が立っている道が古墳への道となります。 |
 |
 |
 |
| こんな道をトボトボトボトボと歩きます。 ゆるやかな登り道です。 途中誰ともすれ違いませんでした。 |
ようやく蝦夷穴歴史センターに到着です。 しかし残念ながら臨時休館です。 (冬期は休みみたいです。) |
ここからさらに150m歩きます。 |
 |
 |
 |
| 途中、気になる刻線が刻まれた石を発見。 これは自然石じゃないですね…きっと。 |
さらに進むと石積みの台座のようなものが! |
ついに古墳に到着! |
 |
 |
 |
| 草は枯れているため古墳の全容が良く分かります。 意外と雄穴と雌穴の入り口は接近しています。 |
この古墳から海が見えます。 とても良い場所に古墳を作ったのですね。 |
古墳の石室案内図。 |
 |
 |
 |
| まずは「雄穴(向かって右手)」を調査しました。 |
ズリズリとかがみながら前進します。 解体調査されているのでキレイに積み上げられています。 |
前方に柵が!
門扉のような石と敷居のような石がありました。 |
 |
 |
 |
| 柵ごしに壁面を観察します。 解体調査時の白線などが残っていました。 内部はきれいに清掃されていました。 |
天井部は角に大きな三角石を載せ、その上に石を積み上げていく技法でこれが高句麗の古墳と似ているらしいです。 |
石室内から外をみています。 |
 |
 |
 |
| 次は左手の「雌穴」を調査します。 こちらは「L字型」の石室です。 |
こちらは柵がないので内部に入ることが出来ます。 |
中は広々。頑張れば住めそうな広さです。 奥の一角が高くなっています。 柩を置いた場所だと思われます。 |
 |
 |
 |
| 部屋の隅はこんな感じです。 |
雄穴と同じように天井部に大きな石がはめ込まれています。 |
羨道と石室を分ける石。 |
 |
 |
 |
| 反対側の石。 ここは敷居がありません。 |
内部から羨道のまぐさ岩を見ています。 |
内部から外を見てみました。 敷石がきれいに加工されていることが分かります。 (完) |